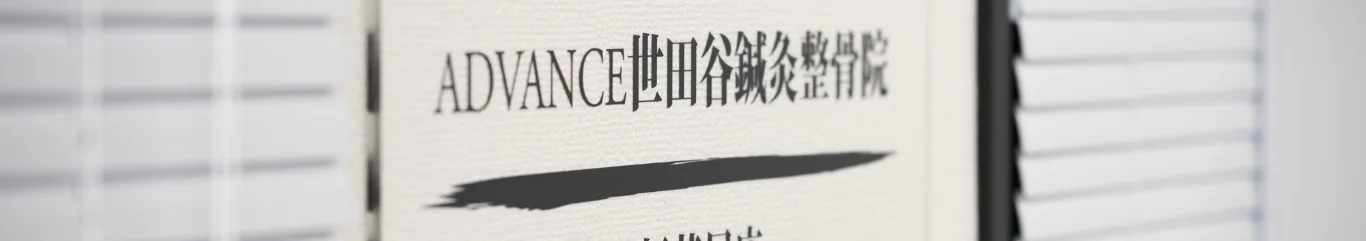
トピックス
- 腰の症状
2025.08.17
坐骨神経痛、何科を受診?症状別で徹底解説!
坐骨神経痛の基本知識
坐骨神経痛とは?
坐骨神経痛は病名ではなく「症状の総称」です。
腰やお尻から太もも・ふくらはぎ・足先にかけて伸びる坐骨神経の経路に沿って痛みやしびれが出る状態を指します。
ℹ️ポイント
症状が足に出ていても原因は腰や骨盤にあることが多いため、痛い部分だけをケアしても根本改善にはつながりません。
症状の種類と特徴
- 痛み: お尻〜太もも裏〜ふくらはぎに、ズキズキ・電気が走るような痛み
- しびれ: 足先までピリピリ・ジンジンした感覚、感覚が鈍くなることも
- 違和感: 張りやつっぱり、長時間の座位や立位で悪化しやすい
- 片側性: 多くは片側のみに出現。両側のときは注意が必要
原因となる疾患について
坐骨神経痛を引き起こす背景には、次のような疾患が関係している場合があります。
- 椎間板ヘルニア: 椎間板が飛び出して神経を圧迫する
- 腰部脊柱管狭窄症: 神経の通り道が狭くなり圧迫される
- 梨状筋症候群: お尻の筋肉(梨状筋)が坐骨神経を圧迫する
- 変形性腰椎症: 加齢などで骨や靭帯が変形し、神経に負担をかける
これらの疾患は整形外科で診断が可能です。
「症状は同じでも原因は人によって異なる」ため、正確な評価と早めの対応が大切です。
どの科を受診するべきか?
坐骨神経痛は、原因の特定(診断)と機能の回復(再発予防)の両輪が大切です。
まずは整形外科での診断→整骨院での全身バランス調整・運動療法という流れが、改善と再発予防を両立させやすい王道ルートです。
整形外科の役割と治療法
整形外科は病態の診断が強みです。レントゲンやMRI等の画像検査で、椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症・骨の異常などを特定できます。
- 薬物療法: 消炎鎮痛薬や湿布、必要に応じてブロック注射
- 保存療法: 安静指導・物理療法・(保険適用の範囲での)リハビリ
- 手術: 重度の神経圧迫や排尿障害など、限られたケースで検討
強い痛み・しびれが続く場合や、赤旗症状(排尿排便障害・会陰部のしびれ・急な筋力低下・発熱)がある場合は、まず整形外科を受診しましょう。
整骨院との違いと選び方
整骨院では自費施術を中心に、痛みの出ている部位だけでなく、骨盤・股関節・体幹・足部まで含めた「全身の使い方」を評価・調整します。
保険の枠組みで行われることが多い整形外科リハビリに対し、整骨院では姿勢・歩行・可動性・安定性まで踏み込んだ改善が可能です。
整形外科と整骨院の“役割の違い”まとめ
- 整形外科: 画像検査で原因を診断し、薬・注射・保険リハで痛みをコントロール。
- 整骨院: 自費で全身の評価と調整を行い、患部に負担をかける動作のクセを修正。運動療法で再発を予防。
- 全身評価: 骨盤の傾き・股関節の可動域・体幹の安定性・足部の崩れをチェック
- 手技・整体: 使い過ぎの筋肉を緩め、使えていない部位を活性化
- 運動療法: ヒップヒンジ・体幹安定・股関節外旋/内転の正しい使い方を指導
- セルフケア: 家でできるストレッチ・フォーム修正・歩行や姿勢のコツ
患部だけのアプローチで良くならない方や、再発を繰り返す方こそ、整骨院の全身×運動のアプローチが有効です。
当院では、整形外科医との連携を踏まえつつ、機能改善と再発予防を重視しています。
ペインクリニックに行くメリット
ペインクリニックは痛みの専門。神経ブロックなどで痛みの悪循環を断ち切る選択肢があります。
痛みが強く日常生活に支障がある場合、整形外科と併用して検討すると良いでしょう。
- 神経ブロック注射: 神経や周囲に薬を投与し痛みを緩和
- 薬物調整: 慢性痛に対する薬のコントロール
- 多面的評価: ストレス・睡眠・活動量なども考慮
痛みコントロールと機能回復は両立可能。
痛みの軽減(ペイン)+原因動作の修正(整骨院)という役割分担が効果的です。
おすすめの受診フロー
-
1.整形外科で診断(必要に応じて画像検査)
2.整骨院で全身評価+手技・運動療法(原因動作の修正・再発予防)
3.痛みがつよい時はペインで痛みコントロールを併用
受診前に知っておきたいこと|整形外科・整骨院・整体院の違い
坐骨神経痛で迷いやすいのが「どこに行くべきか」。それぞれの役割の違いを先に押さえておくと、回復までの道筋がスムーズになります。
| 区分 | 整形外科 | 整骨院(柔道整復師/鍼灸師) | 整体院(民間資格) |
|---|---|---|---|
| 主な役割 | 医師による診断(画像検査等)/薬・注射/保険リハ | 痛みの背景にある全身バランス・動作のクセを評価し、手技+運動で再発予防 | リラクゼーション、独自手技(医療行為ではない) |
| 担当者の資格 | 医師/理学療法士(PT)等 | 柔道整復師・鍼灸師などの国家資格 | 民間資格(法的医療資格ではない) |
| 保険適用 | 保険診療が中心(範囲内でのリハ) | 自費中心のため全身アプローチと運動療法まで実施しやすい | 基本は自費 |
※整形外科のリハビリは主に理学療法士(PT)等が担当します。
一方、整骨院は柔道整復師、鍼灸ははり師・きゅう師などの国家資格者が担当し、全身評価と運動療法を組み合わせやすい点が特徴です。

当院代表 横田就馬
私は整形外科でのリハビリを経験後、当院を開業しました。病院では一日に多くの患者さまを担当するため、患部中心のケアにならざるを得ない場面が少なくありません。
しかし坐骨神経痛は、お尻や骨盤、股関節、体幹など全身の使い方が絡み合って再発を繰り返します。そこで当院では、自費の強みを活かし、手技だけでなく運動療法まで一体で行える体制を整えました。
「痛みを和らげる」だけでなく「再発しにくい体」を一緒につくっていきましょう。
症状別の受診ガイド
腰痛を伴う坐骨神経痛
- まずは整形外科で診断(ヘルニア・狭窄症などの有無を確認)
- 薬やブロックで痛みを抑えつつ、整骨院で骨盤・股関節・体幹の使い方を修正
- 前かがみ・反り姿勢どちらで悪化するか等、動作の癖を評価して再発予防
下肢にしびれを感じる場合
- しびれが強い・進行性・力が入りにくい → 早めに整形外科で検査
- 画像異常が軽微でも、整骨院で梨状筋・ハムストリング等の緊張と姿勢・歩行をセットで改善
- 日常の座り方・荷重癖・靴の影響までチェックすると改善が早い
産後の坐骨神経痛は何科?
- まずは整形外科で危険サインがないか確認(赤旗症状があれば最優先)
- 骨盤周囲の不安定性・筋力低下が絡むことが多く、整骨院で骨盤底筋・中臀筋のリハ+抱っこ・授乳姿勢の指導が有効
- 無理のない産後プログラム(段階的な体幹・股関節トレ)で再発を予防
坐骨神経痛の治療法
坐骨神経痛の治療は、① 痛みのコントロールと② 再発を防ぐ体づくりの両輪で進めると効果的です。
ここでは「保存療法」「手術が必要なケース」「理学・運動療法」の流れをわかりやすくまとめます。
保存療法と薬物療法の違い
保存療法は、手術以外で痛みを抑えながら自然回復を促す方法の総称です。症状の強さや期間に応じて、次のような対処を組み合わせます。
- 薬物療法: 痛み止め・神経痛に用いる薬剤などで痛みをコントロール
- 注射療法: ブロック注射で炎症や神経の過敏を一時的に抑える
- 物理療法: 温熱・電気などで筋緊張や循環をサポート
- 安静と活動量の調整: 悪化動作を回避しつつ、固まらない範囲で日常動作を維持
※薬や注射は「痛みの波をならす」役割。痛みが落ち着いたら、次の段階(運動療法)へ進むと再発予防に繋がります。
手術が必要なケースとは?
画像検査で明らかな神経圧迫があり、強い痛みや進行性の筋力低下が続く場合は手術が検討されます。次の赤旗サインがあるときは、速やかに医療機関へ。
- 排尿・排便障害、会陰部のしびれ
- 急激な筋力低下(つま先・かかとが上がらない 等)
- 発熱や外傷を伴う痛み など
※多くの坐骨神経痛はまず保存療法で改善が期待できます。手術の判断は、症状の推移・神経学的所見・画像所見を総合して行われます。
理学療法・運動療法(整骨院でのアプローチ)
痛みが落ち着いてきたら、再発を防ぐ体づくりへ。患部だけでなく、骨盤・股関節・体幹など全身の使い方を整えます。
- 評価: 立ち方・座り方・歩行、股関節の可動域、中臀筋などの筋力バランス
- 手技: 梨状筋・ハムストリング等の過緊張を緩め、荷重ラインを最適化
- 運動: 骨盤底筋・中臀筋の活性化、ヒップヒンジ、体幹の安定化、呼吸再教育
- セルフケア: 仕事環境の調整(椅子・デスク高)、座りすぎ対策、日常のストレッチ
進め方の目安: 痛み軽減期(週1〜2) → 機能改善期(週1+ホームエクササイズ) → 定着・再発予防(月1メンテ)
治療の組み合わせとタイミング
-
1.急性期: 痛みのコントロール(薬・注射・物理療法)+悪化動作の回避
2.回復期: 手技で過緊張を緩めつつ、股関節・体幹の安定と基本動作の再学習
3.再発予防期: 生活動作・姿勢・歩行の最適化、中臀筋・体幹の継続エクササイズ
坐骨神経痛を解消するセルフケア
ご注意: セルフケアはあくまで補助的な対処です。痛みが増す・しびれが強くなる・力が入りにくい等の変化が出た場合は中止し、医療機関や当院へご相談ください。
- 妊娠中・持病のある方は事前に専門家へご相談ください。
- 反動をつけず、気持ちよく伸びる範囲で行いましょう。
- 呼吸を止めず、ゆっくり行うのがコツです。
① 梨状筋ストレッチ
椅子に浅く腰掛け、片足を反対の膝の上に乗せます。背筋を伸ばしたまま、ゆっくりと上体を前に倒していきましょう(左右各30秒)。
お尻の奥がじんわり伸びる感覚があればOKです。

② ハムストリングスストレッチ
仰向けになり、膝を軽く曲げた状態から片脚を天井に向けてまっすぐ伸ばします。タオルやバンドを足裏に引っかけ、自分の方へゆっくり引き寄せましょう(左右各30秒)。
太ももの裏側に軽い伸張感があれば、正しくできています。

③ サイドレッグレイズ
横向きに寝て体を一直線に整え、上側の脚を真横に持ち上げます。外くるぶしが正面を向いたまま上げ下げを行いましょう(10回×3セット)。
骨盤が前後にブレないように注意してください。

④ ドローイン(腹式呼吸エクササイズ)
仰向けで両膝を立て、お腹をふくらませながら鼻から息を吸います。ゆっくり口から吐きながらお腹をへこませましょう(10回×3セット)。
腰が反らないよう背中を床につけたまま行うのがポイントです。

セルフケアを続けても改善が乏しい場合や、不安がある場合は専門家の評価が有効です。
当院では神経の走行・骨盤アライメント・股関節機能まで含めた全身評価と、症状に合わせた施術・運動指導を行っています。

